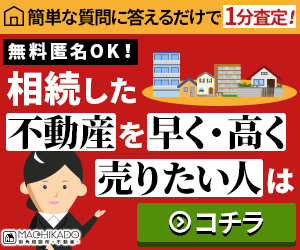名義人が死亡した場合は口座を凍結しなければいけない
死亡した名義人の銀行の口座は放置してはいけません。そして、そのまま口座を使用することもできません。
ただし死亡届を提出したとしても、その情報が銀行にまで届くのかといえばそうではありません。
銀行に口座の名義人が死亡した、ということを報告していないなら、凍結されないので使用できます。
家族が亡くなられたのであれば、まずは銀行に死亡したということを報告しなければなりません。
その連絡をすることで銀行口座は、初めて凍結されます。
トラブルを避けるために凍結する
「使えるならそのまま使えば良いのに」と思う方もいるかもしれません。
ですが、例えば親の口座の名義を子供名義にして利用する、ということももちろん可能ですが、それではトラブルの原因になることがあります。
銀行口座に入っているお金は相続財産になります。
そのため遺産分割の対象となりますし、相続税における課税対象です。
銀行口座を凍結しなければ、どこからどこまでが相続財産なのかを判断することができなくなってしまいます。
亡くなった時、故人の預金などを勝手に引き出す人がいるのです。
そのため、銀行口座を凍結してから一度お金を引き出せないような状態にしなければなりません。
口座の凍結は、銀行にただ亡くなったことを報告するだけで完了します。
銀行にとってもリスクがあり、亡くなった人の口座をそのまま放置していると、勝手にお金を引き出されたなどと親族からのクレームを受けることになってしまいます。
葬儀費用を相続財産から出したい時は凍結する前に下ろす

葬儀の費用を死亡した人の口座から支払いたい場合は、法定相続人全員にしっかりと了承を受けた上で、口座を凍結してもらう前に葬儀費用だけを下ろすようにします。
葬儀費用を一部の相続人が負担した場合、その分は資産分割での調整が行われます。
葬儀費用は、相続税の課税評価額を計算する場合、控除の対象になります。
そのため、葬儀費用を誰かが立て替えられるのであれば、立て替えておくと後々面倒ではなくなるのでおすすめです。
口座凍結よりも前に預金の引き出しをするのなら、法定相続人すべてに了承を得ておくことを忘れてはなりません。
そうしなければ、持ち逃げされてしまったと勘違いされることがあるので注意してください。
やはり理想として、死期が近いとわかっている場合には本人が葬式費用事前に用意しておくというのがベストです。
生前に葬儀社で見積もり依頼をして、金額もしっかりと把握しておくようにすると、いざとなった時にトラブルなどの原因になることもありません。
身近に葬式費用を出せる人がいればいいですが、いないような場合には生前に本人から葬式費用を預けてもらうというのがいいかもしれません。
葬式費用は預けていたものの、お金を使い込まれてしまうというリスクもゼロではありません。
そのため、全く関係のない第三者にお金を預けておくということも可能です。
凍結解除にはいくつかの書類が必要
凍結した口座を凍結期間中に解除したいと思うのであれば、いくつかの書類が必要になります。
被相続人の銀行口座が凍結され、お金を引き出せない状態で高額な医療費を請求されることもよくあります。
そのような場合には、凍結された口座からお金を引き出さなければなりません。
払い出しと呼ばれる手続きをすることによって、凍結後でも現金を引き出すことはできます。
払い出しにはいくつかの書類が必要になります。
- 被相続人の戸籍謄本
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の同意書
- 相続人全員の印鑑証明
- 相続人の実印
- 銀行のキャッシュカード
- 払い出しをする人の身分証明書
凍結中である預金残高は資産分割がしっかりと確定するまでは、法定相続人すべての共有財産になります。
もしも法定相続人であったとしても、一人で払い出しをしてもらえるのかといえばそうではないのです。あくまで共有財産ですので、必要な書類などをしっかりと集めなければお金を下ろすことはできません。
この払い出しに必要な手続きは、弁護士でも対応してもらうことはできます。
凍結された口座からお金を引き出す手続きは簡単ではありません。
そのため、なかなか自分では行うことができない、という方もいると思います。
そのような場合、遺産相続の手続きを弁護士に依頼すると、払い出しをしたくなった時に書類の手続きを代行してもらうことができます。
速やかに凍結をしないと持ち逃げされる可能性がある

被相続人が死亡したのにも関わらず報告せずにいれば、そのまま使用できます。
キャッシュカードの暗証番号などがあれば、現金は普通に引き出すことができます。
このようなことから、相続財産の持ち逃げが非常に多く発生しています。
ただし、銀行の口座を凍結しても、凍結するまでのほんの短い時間でお金を引き出されることもあるわけです。
ですので、本人が死亡したらなるべく早く金融機関で、誰もお金を下ろすことができないように凍結する必要があります。
そうすることで、持ち逃げなどを未然に防ぐことができます。
また、財産を持っている本人がまだ生きているにも関わらず、お金を勝手に引き出されてしまうこともあります。
例えば病気などであれば、病院で親族全員が集まっているようなこともあるでしょう。
バタバタしている時に、こっそりと現金を引き出すというような人もいるのです。
死亡する直前は、亡くなっていないので口座も凍結されていません。お金を持ち逃げされる可能性が高くなってしまいます。
そうならないように、ある程度死期が近づいたとなれば、キャッシュカードや印鑑などといった大事なものは安全な場所にしっかりと保管しておくようにしてください。
口座凍結をしてから預金残高証明書を取得し、予想よりも残高が減っているのであれば、誰かがお金を引き出した可能性があります。
そのような場合、取引履歴明細証明書を発行してもらうと、いつどれくらいのお金が引き出されたのかというのをすぐに判断することができます。
持ち逃げをされても返還を求めることは可能
お金の持ち逃げは不当利得と呼ばれるものに分類されますので、不当利得返還請求によって返還を求めることも可能です。
もしもお金を持ち逃げした人が法定相続人であったとしても、法定相続分を大幅に超えているような場合には不当利得になりますので、返還を求めることができます。
ただし返還を求めたとしても、持ち逃げするほど経済的に苦しい場合には返還してもらうまでの時間が長くかかってしまうこともあります。
そのため個人の預貯金の持ち逃げなどで疑われるのであれば、できるだけ早く書類を集めて対処するようにしなければなりません。
このように、亡くなった人の口座に関して親族間でトラブルが発生したりする場合がありますので、トラブルにならないよう対策をするか、亡くなった後は速やかに口座を凍結するなどしなくてはなりません。
事前にしっかりと、やらなくてはならないこと、必要なものなどを確認しておきましょう。